「「ファインマン物理学」を読む <量子力学と相対性理論を中心として>」 竹内 薫著 [お勉強]
初心に帰ってと言うよりも、昔ファインマン大先生がカルテックでの講義で学生に伝えた
かった本質的な事が分かる様な解説になっています。もう一度この本を併読しながら、再度
頑張って「ファインマン物理学」を読み直してみようと思いました。
「ファインマン物理学」訳本全5巻は、物理の勉強をちゃんとしておこうと思い立って10年
くらい前から2~3回通読しました。日本の学部レベルの物理学の教科書とは異なり、ファイ
ンマン独特の内容だと感じます。全ての道は量子力学に続くという感じで、ファインマンは
講義(力学、電磁気学等も含めて)を通して、最終的に学生が量子力学の入門として、正し
く(ファインマン流に)理解できるように誘導しているのだと思います。講義の内容が文章
化されたテキストをただ読んでも、浅学な私の様な者にはそれを読み取るのは難しいと思い
ました。
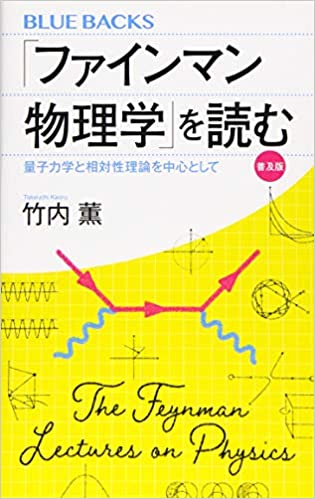
続いて同著の<電磁気学を中心として>、<力学と熱力学を中心として>も読んでいる途
中です。
私が学生の時の電磁気学の教科書はアメリカの大学の工学部向けのものだったと思います。
優秀な諸君は分かるでしょうと、先生はどんどんと授業を進めました。「優秀」な同級生
は別として、私なんぞは英語の教科書を読むだけでも四苦八苦していたので、矢尽き旗折
れてしまいました。今思えば、専門用語さえ分かっていれば、さほど難しい英文ではなか
ったのですが。(^^;
その後、3年生か4年生の時、当たり前ですがちゃんと電磁気学は勉強しておかなくてはいけ
ない、という自覚はありましたので、ファインマンの「電磁気学」を買いました。いきなり
マックスウエルの方程式から始まっているのには、これは学部向けの教科書なのだろうかと
当時は面くらいました。電磁気学の集大成であるこの方程式から光速が導かれる事が物理学
としては最も重要だからファインマンは最初に出したのでしょう。
いずれにしても、必修科目なので既にお情けで可をもらっていたので、時すでに遅しでし
た。(^^;
今更こんな事を書いても何にもなりませんが。(^^;




当方電磁気学は,学生時代電気学会編とバークリー物理学コースなどで学びましたが,どれも???でした。古典的名著としてはストラットンを勧められましたが持っていません。ファインマン物理学の訳本も持っていますが,マックスウェル方程式を理解するためには幾つかのステップがありますね。
・ベクトル解析の意味と演習
・ガウスの定理の理解
・アンペールの法則の理解
その前に,E,H,D,B各量の正確な把握などでしょうか。
分かる人からすれば,麓のごちゃごちゃした入り口はどうでも良く,頂のマックスウェル方程式から説明したくなります。しかし何も分からない学生にはとってはちんぷんかんぷんが延々続く状態。そのことすら忘れていました。
後年,共立出版の「物理学OnePoint」の「EとH, DとB」長沼伸一郎の「物理数学の直感的方法」あたりでようやく納得できる状態になったと思います。
あと,電磁気学は単位を押さえると分かった感じになると思います。
量子力学に関してはDiracや朝永さんのものを少し読みましたが,小出昭一郎さんの「量子力学(I)」が最もわかりやすく教育的だと思います。
by Enrique (2020-08-26 07:55)
Enriqueさん
長沼伸一郎の「物理数学の直感的方法」はいいですね。学生時代に読んでいたら、もうちょっと成績も良かったかもれません。(^^;
小出昭一郎先生の「量子力学(Ⅰ)」は量子力学基礎の教科書でした。勿論単位は取れませんでした。(^^;
何年か前に、古本で(Ⅱ)を買いそろえました。
まだ私の量子力学のレベルは、ファインマンと小出先生の本で足踏み状態が実情です。
by たこやきおやじ (2020-08-26 10:51)